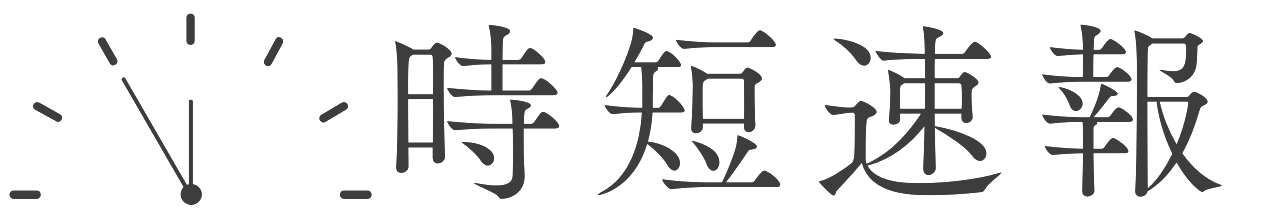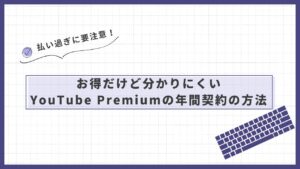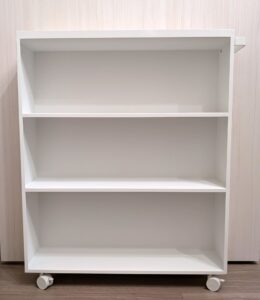最近食品の値上がりがエグい。令和の米騒動なんて言って米が取り沙汰されているが米だけじゃない。何もかもがすごいペースで値上がりしてる。
食品の値上がりがエグすぎてさすがに家計への影響がバカにできなくなってきたので一ヶ月の食費を全て記録してみることにした。リアルな夫婦二人暮らしの食費ってどんなものだろうかと気になる人はぜひ見ていってほしい。

おいらーです。社会人歴5年目の社畜サラリーマン。あまりの仕事量に効率化に目覚め、仕事の効率化・家事の効率化を模索し続けている社畜。X(Twitter)やってます。
【はじめに】なぜ食費がこんなに上がっているのか


最近スーパーへ行くたびにその価格に驚く。この8月にも乳製品を中心に相当な数の食品が値上げされた。いつも買っているヨーグルトが20%以上値上がりしてたんだから驚くほかない。この8月の乳製品の値上げは飼料価格の高騰等のために生乳の価格が上がったことによる。
昨年から世間を騒がしている米の価格高騰は続く不作や買い占めが一因と言われている。その他、ロシアウクライナ問題による輸送費高騰や円安による輸入価格高騰など様々な要因が重なって諸々の値上げが起きている。
総務省統計局の調査によれば、2024年の二人世帯かつ勤労世帯の食費平均値は75,254円となっている。ちなみに2024年の二人以上世帯の食費の対前年実質増減率は-0.3%と実は減っている。ただ、これは相次ぐ値上げに節約意識が高まっていることが反映されている気がするので食費の値上がりが起きていないということではないだろう。
そんなわけでこの記事では食費の値上がりを肌でひしひしと感じている我が家のリアルな食費を公開しようと思う。そして食費を公開するだけでなく、そこから見えた課題と食費節約の方法も考察しようと思う。
【食費公開】我が家の7月のリアルな食費
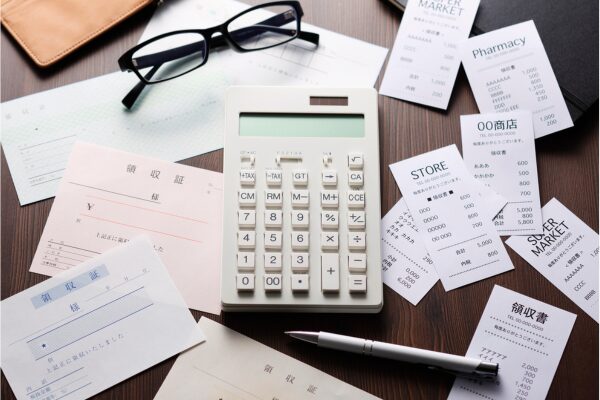
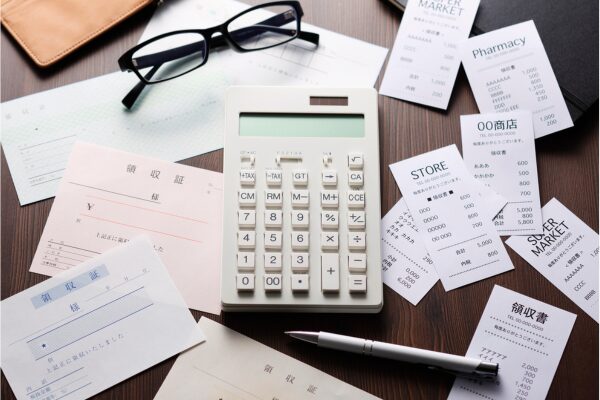
結論から言うと夫婦二人暮らしの我が家の7月の食費は70,372円だった。2024年の平均値よりも下回っているので結構頑張ったと思う。ただ、カウントされてない費目があるので厳密には異なる。
一つは米だ。ふるさと納税の返礼品の米があるため購入していない。だいたい月に5kg弱ほど消費しているので今の相場だと4,000-5,000円相当が計算に入っていないことになる。
もう一つはプロテインだ。これはAmazonプライムデーの際などにまとめ買いしているため計算に入っていない。平日の朝に1杯飲んでいるので月あたりだいたい3,000円相当が計算に入ってないことになる。
これらを含めると概ね平均と同程度の食費ということになる。もう少し節約したいところだ。
費目ごとに分けた金額も集計してみた。それが以下の表だ。次の章ではこの費目ごとの集計を見つつ、食費を節約する方法について考えていこうと思う。
| 費目 | 金額 |
| 自炊用 | 41,548円 |
| 中食 | 2,840円 |
| 外食 | 3,402円 |
| 昼食(平日出社時) | 10,118円 |
| 間食 | 12,464円 |
| 合計 | 70,372円 |
【分析】我が家の食費の良かった点と改善点
費目ごとの食費を見ていると我が家の食費の良かった点と改善点が浮かび上がってくる。ここでは我が家の食費から見えてくる良かった点と改善点を見つめながら今後の方針を考える出発点にしようと思う。
【よかった点①】自炊が中心の生活
まずよかったのは自炊が生活の中心だったことだ。自炊中心の生活は今始めたことではなく同棲以来ずっと続けていることではあるが、この物価高の時代に惣菜や外食中心の生活をしているとお金がいくらあっても足りないのでいい習慣だと自負している。
自炊は2人で分担しつつ、基本的に凝った料理はせずに定型にすることで平日も自炊で生活できるよう工夫しているがそれはまた別の話。
【よかった点②】外食がほとんどない
自炊中心生活の裏返しであるが、外食がほとんどなかったことも良かった点だ。忙しいとつい外食で済ませたくなるのだが、そこをぐっと抑えることができていたのもよかった点だ。
【改善点①】出社時の昼食代コストダウン
良かった点もあったが、改善点も見つかった。まずは昼食代だ。夫婦2人の出社時の昼食代を合算したものなので抑えられている方ではあると思う。ただ、やはり自炊に比べると1回あたりの金額は高くなってしまう。
テレワークもあるため、出社日数自体が少ないが、それでも1万円になっているので工夫をする余地がありそうだ。
【改善点②】間食が多い
間食が多すぎる。コーヒーなんかも含まれてはいるのだが、最近は会社では会社に備え付けられているドリップバッグ式のコーヒーを飲むようにしているので節約はされているのだが、それ以外にも間食が多すぎる。
最近はチョコレートを始めお菓子の類の高騰も激しく、その影響をもろに受けている。二人で楽しくお菓子を食べる時間は幸せな時間なので全くなくすというのも味気ないが、とはいえ健康には何のメリットもないのでさすがにもう少し減らすべきだ。
【解決策】今後の食費節約の方針
【方針①】お弁当持参での昼食代節約


まずは出社時の昼食代節約の方針だ。出社時にお弁当を買ったり外食をしてしまうから食費がかさんでしまう。7月に食費を記録していて昼食代が膨れてくるのが気になったため実は途中から導入していたのだが、簡易的なお弁当を持っていくことにした。
とはいえ、忙しい朝にしっかりとしたお弁当を作ることは難しいのでタッパーに前日の夜ご飯として炊いた米を詰めて梅干しとかふりかけをかけたものだけを用意する。もちろんこれだけではあまりにもひもじいのでAmazonプライムデーなどでまとめ買いした紙パックのプロテインも持っていく。あとは会社の近くでカップみそ汁など1品だけ追加するという昼食だ。
昼食の一部を持参するという発想で手間をなるべく削減しながら節約を実現するという作戦である。プロテインと米が合わないという意見もありそうだが、このお弁当のポイントは昼食の30分ほど前にプロテインを飲んでおくところにある。プロテインはお腹にたまるので昼食前に飲んでおくとこのお弁当だけで結構お腹いっぱいになる。
スープジャーなどを買って汁物も持参するかは今検討中である。ちなみにお弁当箱を洗う手間も削減したいので当然食洗器対応のタッパーを使っている。スープジャーを買う場合は食洗器対応のものを探すつもりだ。
【方針②】間食へのルール導入


上述の通り、我が家の間食はさすがに多すぎる。とはいえ全くなしというのもさみしいし突然なくすとストレスで苦しくなりそうなのでルールを導入しようと思う。
まずは、平日の間食大幅減だ。平日は仕事を終えて夕食を作って、としているうちに遅くなるのだから、少し間食の量をセーブしようと思う。小分けの袋1-2袋などにセーブしてもそこまでストレスはたまらないと思う。というかそれが健康的にもいい。
そして土日は逆に制限を少し緩めようと思う。急に変えすぎるとストレスにもなるし、土日は平日の疲れ・ストレスを癒す時間として大切にしたいので、おやつの時間には好きなものを食べるといった形で楽しくそこそこのルール運用にしようと思う。
【方針③】自炊の見直し


食費の中で最も金額比率が大きいのは当然自炊のための食費である。そこでこの自炊についても中長期で見直していきたい。
自炊をする上で我が家には実は致命的な弱点がある。それは冷蔵庫が一人暮らし時代のものであるということだ。一人暮らし用としては大きめの冷蔵庫を買っていたためそのまま使っているのだが、さすがに二人暮らしでまとめて買ってくると入りきらないし、野菜室など専用のスペースがないため野菜のもちが悪い。そのため中長期の計画で、冷蔵庫の新調と合わせて自炊用の食材の買い方を変えていきたいと思っている。
大きくて性能のいい冷蔵庫を導入すれば食材のもちや冷凍できる量が増えて選択肢も増えるためもっと工夫ができるはずだ。
【方針④】カフェやコンビニでのコーヒー購入禁止


これはすでに徹底しているのだが、カフェやコンビニでコーヒーを買わないようにしている。カフェでコーヒーを買えば300円は下らないし、コンビニでも150円近くする。これを平日毎日買っていたら月で3,000~6,000円にもなってしまう。
そのため会社では会社が用意してくれているドリップバッグ式のコーヒーを飲むようにし、家ではレギュラーコーヒーで入れるようにしている。冬であれば水筒に温かいコーヒーを自分で入れて持ち歩くのもおすすめだ。
【方針⑤】ふるさと納税の活用


冒頭にも書いた通り、我が家は米をなるべくふるさと納税の返礼品で賄うようにしている。ふるさと納税というと始まった当初はちょっとした贅沢として牛肉やフルーツなどを返礼品としてもらっている人も多かったようだが、この物価高の時代、生活必需品に使うのがおすすめだ。
我が家ではだいたい夏から秋にかけてまとめて注文して次の年まで毎月届くようにしたりしている。このおかげで最初に米不足・米高騰が叫ばれだしたときには焦ることもなく、しかも前年の価格で米を確保できていた。最近は米高騰の煽りを受けていて、高くなっているし毎月配送などの良い条件もなくなってきている点は玉に瑕。
【方針⑥】外食は月に1回


これは少し前から導入しているのだが、妻との外食は月に1回にしている。
外食をして「自炊をしなかった」という罪悪感を持つのもそれはそれでせっかくの外食が楽しくないし、かといって全くしないのもそれはそれで味気ない。なのでその折衷案として月1回二人で楽しく外食に行くことにしている。
こういうほどよいルールを作ると次はどこに行こうかという会話も生まれるし、その1回は気兼ねせず楽しむことができるのでおすすめだ。
【まとめ】賢く、楽しく、食費と向き合う
何度でもいうが、ここ1-2年の食費の高騰はあまりにも苦しい。ただ、その影響で安いからと極端に同じものばかり食べたり、楽しみにしていた食事を削ってしまうと続くものも続かなくなってしまう。うまく食事を楽しめるルール作りをしつつ、ふるさと納税やお弁当持参など賢く対策もしながら食費を向き合っていかないといけない。